
日産自動車。日本を代表する自動車メーカーであり、世界中にその名を知られるグローバル企業です。
しかし、この巨大企業が過去に「倒産寸前」とまで囁かれるほどの危機に瀕していたことをご存存じでしょうか?なぜ、日産はそこまでの窮地に追い込まれたのか。
本記事では、その複雑な要因を多角的に分析し、日産がどのようにしてその危機を乗り越えようとしてきたのかを深掘りします。
- 日産がなぜ危機に陥ったのか、その複雑な要因についてわかる。
- カルロス・ゴーン氏によるV字回復の裏側と、その功罪についてわかる。
- 現在の経営課題と、未来に向けた日産の戦略についてわかる。
- 日産を応援する人々の多様な声や期待についてわかる。
過去の栄光と綻びの始まり:バブル経済と拡大路線

日産の歴史は華々しい成功に彩られていますが、その綻びは意外な時期に始まっていました。
1980年代後半のバブル経済期、日本企業全体がそうであったように、日産もまた積極的な設備投資と生産能力の拡大路線を突き進みました。
国内市場の成長を背景に、新車種を次々と投入し、販売台数を伸ばしていったのです。
しかし、この拡大路線には大きな落とし穴がありました。バブル崩壊後、日本の景気は急速に冷え込み、自動車市場も例外ではありませんでした。
過剰な生産能力と、それに伴う固定費の増大は、日産の経営を圧迫し始めます。
経営の硬直化と失われた競争力
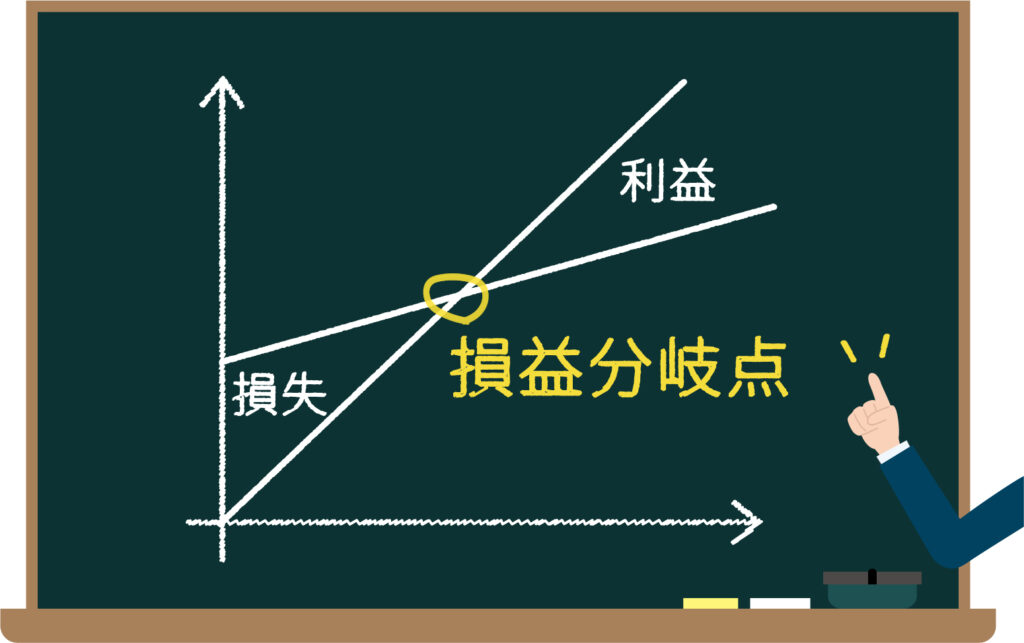
バブル崩壊後も、日産の経営体質はすぐに変わることはありませんでした。
長年の成功体験が経営層に蔓延し、意思決定は硬直化。市場の変化への対応が遅れ、新しい技術やデザインへの投資も停滞しました。
結果として、国内外の競合他社に比べて競争力が低下し、魅力的な商品が生まれにくくなっていきました。
特に深刻だったのは、高コスト体質です。
過剰な設備、非効率な生産プロセス、そして過剰な従業員を抱えることによる人件費の負担は、日産を蝕んでいきました。研究開発費も十分に確保できず、将来を見据えた技術開発にも遅れが生じました。
迷走する戦略と負の遺産
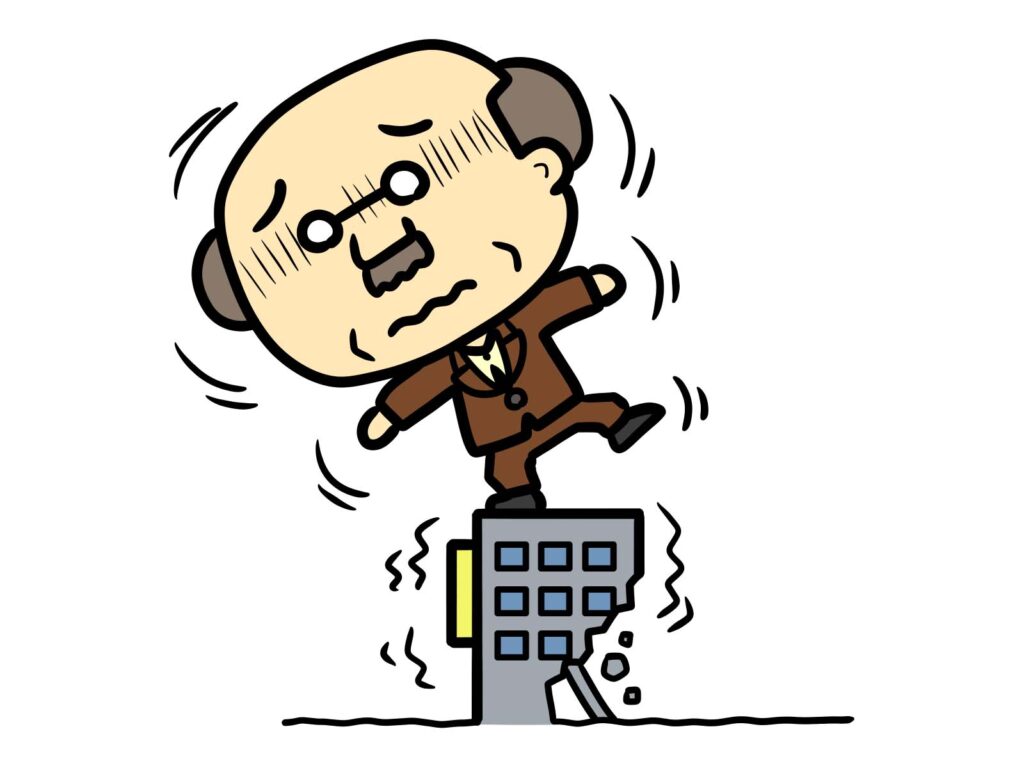
この時期の日産は、明確な経営戦略を見失っていたと言わざるを得ません。
「選択と集中」が叫ばれる中で、日産は多くの車種を抱え、車種間のコンセプトが曖昧になるなど、ラインナップの整理も進みませんでした。
加えて、国内販売網の弱体化も深刻な問題でした。ディーラーへの支援が手薄になり、販売現場の士気も低下。結果として、販売台数は低迷の一途を辿ります。
さらに、過去の過剰な投資が「負の遺産」として日産に重くのしかかりました。工場稼働率の低下による減価償却費の負担、そして多額の有利子負債は、日産の財務状況を極めて脆弱なものにしました。
銀行からの追加融資も困難になり、まさに「倒産寸前」の瀬戸際まで追い込まれたのです。
カルロス・ゴーン氏の登場と「日産リバイバルプラン」

このような絶望的な状況の中、日産を救うべく現れたのが、ルノーから派遣されたカルロス・ゴーン氏です。
1999年、日産はルノーとの資本提携を発表し、ゴーン氏がCOO(最高執行責任者)に就任します。彼の登場は、日産にとってまさに「劇薬」でした。
ゴーン氏が就任してすぐに打ち出したのが、「日産リバイバルプラン」です。このプランは、以下のような大胆かつ具体的な施策から成り立っていました。
- 工場の閉鎖と生産能力の削減: 過剰な生産能力を解消するため、国内外の工場を閉鎖し、生産ラインを再編。
- サプライヤーの見直しとコスト削減: 部品調達先の再編や、共同購入による価格交渉で徹底的なコストダウンを敢行。
- グループ会社の再編と売却: 本業に集中するため、関連性の低いグループ会社を売却。
- 車種ラインナップの抜本的見直し: 不採算車種の廃止、新型車の投入加速。
- 「クロスファンクショナルチーム(CFT)」の導入: 部門横断的なチームを編成し、意思決定の迅速化と責任の明確化を推進。
- 成果主義の徹底: 年功序列を廃し、実績に基づいた評価・報酬制度を導入。
これらの施策は、日産社内に大きな抵抗を生みましたが、ゴーン氏は躊躇なく実行に移しました。
「コミットメント(必達目標)経営」を掲げ、達成できなかった場合は責任を問うという厳しい姿勢で臨んだのです。
結果として、日産は驚異的なスピードで業績を回復させます。就任からわずか2年で有利子負債を完済し、翌年には過去最高益を達成するまでに至りました。
このV字回復は、「ゴーン・マジック」と呼ばれ、世界中で大きな注目を集めました。
ゴーン体制下の光と影:そして再びの試練

ゴーン体制下で日産は息を吹き返し、EV(電気自動車)の「リーフ」など、先進的な取り組みも積極的に行いました。しかし、その輝かしい成功の裏には、新たな問題の種が潜んでいました。
一点目は、ルノーとのアライアンスのあり方です。 ルノーは日産の筆頭株主であり、日産の経営に対する発言力は非常に強いものでした。
ゴーン氏がルノーのCEOも兼任するようになると、日産の意思決定がルノーの意向に左右される場面も増え、日産の独立性が損なわれているという懸念も浮上しました。
二点目は、ゴーン氏への権力集中と企業統治の問題です。 圧倒的な実績を背景に、ゴーン氏への権力は集中し、社内のチェック機能が十分に機能しなくなっていったという指摘があります。
これが、後に彼が逮捕されることになる金融商品取引法違反の疑いへと繋がる遠因となったとも言われています。
そして、ゴーン氏の逮捕と退任後、日産は再び大きな試練に直面します。アライアンスの求心力低下、幹部交代による経営の混乱、そして世界的な自動車市場の変革期という三重苦です。
現在の日産と未来への挑戦

ゴーン氏の退任後、日産は立て直しを図るべく、「Nissan NEXT」という新たな事業構造改革プランを打ち出しました。
これは、 unprofitable な事業の整理、生産能力の最適化、そして電動化と自動運転といった次世代技術への重点投資を柱としています。
- 事業の選択と集中: 収益性の低い事業や車種の整理を進め、コア事業に経営資源を集中。
- 生産能力の最適化: 世界的な需要変動に対応できる柔軟な生産体制を構築。
- 電動化の加速: EVだけでなく、e-POWERなどの独自の電動化技術の普及を推進。
- コネクテッドカー・自動運転技術の開発: モビリティサービス分野での競争力強化。
日産は現在、この「Nissan NEXT」を着実に実行に移し、収益性の改善と企業体質の強化に努めています。また、ルノーとの関係性も、より対等なパートナーシップへと見直しの動きが進んでいます。
過去の「倒産寸前」の経験から得た教訓を活かし、日産は今、持続可能な成長を目指し、未来のモビリティ社会をリードする存在となるべく、挑戦を続けています。
ファンや視聴者のコメント
ここでは、日産を応援する方々や、日産のこれまでの歩みを見てきた方々の声を紹介します。
Aさん(50代男性、長年の日産車オーナー): 「昔の日産は本当に元気で、スカイラインなんて憧れの的だった。ゴーンさんが来てからは業績も戻ったけど、なんか昔のワクサク感が薄れた気がするんだよね。今の新しい車はすごくいいのもあるし、また昔みたいにワクワクさせてくれる車を出してほしいな。」
Bさん(30代女性、EVに興味あり): 「リーフに乗ってるんですけど、EVの走りって本当に素晴らしいです。日産にはEVのパイオニアとしての誇りを持って、もっと魅力的なEVを出してほしい。充電インフラとか、もっと充実してくれると嬉しいです。」
Cさん(40代男性、自動車業界関係者): 「日産が倒産寸前だったのは業界では有名な話だけど、よくここまで立て直したと思います。ただ、ゴーンさんの後遺症はやっぱり大きいですよね。アライアンスの見直しとか、大変なことも多いと思いますが、頑張ってほしいです。」
Dさん(20代男性、若手エンジニア志望): 「日産って技術の日産って言われてたんでしょ?昔の車を見ると、本当にすごい技術力だったんだなって思います。今は電気とか自動運転とか、新しい技術がどんどん出てきてるから、日産にはもっと攻めた開発をしてほしいです!」
Eさん(60代女性、日産株主): 「私はずっと応援してるわ。ゴーンさんの時はびっくりしたけど、またちゃんと日産らしくなってくれることを願ってる。日本の技術力が世界に誇れるように、頑張ってほしいわね。」
これらのコメントからもわかるように、日産に対する期待と、今後の動向への関心が非常に高いことが伺えます。
まとめ:過去の教訓を未来へ繋ぐ
日産が経験した「倒産寸前」の危機は、企業経営における数々の教訓を私たちに示しています。市場の変化への対応の遅れ、経営の硬直化、高コスト体質、そしてリーダーシップの重要性。
これらの要因が複雑に絡み合い、日産を窮地に追いやったのです。
しかし、ゴーン氏による大胆な改革、そしてその後の新たな経営体制による立て直しの努力により、日産は再び前を向いて歩み始めています。
電動化、自動運転、コネクテッドカーといった新たなモビリティの潮流の中で、日産がどのようにその存在感を示していくのか、今後の動向から目が離せません。
過去の失敗から学び、未来へ繋ぐ。日産の挑戦は、これからも私たちに多くの示唆を与えてくれることでしょう。




コメント